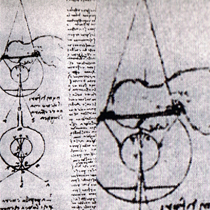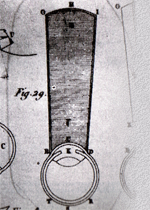HOME >
最先端“望遠コンタクトレンズ”☆
2013.07.05|shiozawa
多くの人がごく日常的につけている“コンタクトレンズ”。
現在の製品でも、十分よく見えるようになりますし、値段も手ごろなんですが、
最先端技術のコンタクトレンズはプラスアルファですごい機能がついてきそうです。
■世界初! 倍率切替可能な「望遠コンタクトレンズ」
目に装着するだけで「望遠鏡」になる画期的なコンタクトレンズが開発された。
通常のコンタクトレンズと変わらない薄さで、通常視覚の約3倍もの望遠効果が得られるものだ。
加齢黄斑変性症の視覚補助器具としても実用化が期待されている。
左は「望遠コンタクトレンズ」の外観。
直径8mm、最大厚さ1.17mm。右は3D眼鏡と組み合わせた様子。
偏光フィルターによって中央の穴への光の入射を切り替える。
実はほかにも「望遠コンタクトレンズ」の開発は行われている。
しかしいままで開発されたものは4mm以上の厚みがあり、実用上の大きな課題になっていた。
今回新しく開発されたレンズは、最も厚い部分でも1.17mmしかない。
装着した際の違和感も小さく、実用化へ大きく近づいた。
この「望遠コンタクトレンズ」は、誰でも装着することができる。しかしこの技術を最も待ち望んでいるのは、加齢黄斑変性症患者だろう。
加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って網膜に異常が生じ、最悪の場合は失明にも至る疾患で、その患者数は全世界で増加している。iPS細胞の最初の臨床試験の対象としても話題となった疾患だ。
今回の「望遠コンタクトレンズ」は、加齢黄斑変性症患者にとって、心理的にも受け入れやすい視覚補助器具になると期待されている。
引用:Wired.jp
これはなかなかすごいです。
人には備わっていない望遠機能が今までのコンタクトレンズと同じように装着するだけでできてしまう。
本来の役割の“視力の補助器具”としての機能を完全に超えてます☆
バードウォッチングが望遠鏡や双眼鏡なしでできそうです。
また、軍事関係では特に使われそうな予感がします。
最先端もあれば、もちろん歴史もある。
ということでコンタクトレンズの500年の歴史をちょこっと紹介。
実は歴史はいがいと長いんですね。
<コンタクトレンズの歴史>
■1508年 Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ)
ルネッサンス時代、ガラスの壺に水を入れ、顔をつけて目を開けたところ、外の景色が変わった事からコンタクトレンズの原理が発見されたと言われています。
水を満たした球形の容器に眼をつけるイラストを使って、その視力矯正効果を論じています。
ダ・ヴィンチはコンタクトレンズの原理の創案者であると考えられております。

レオナルド・ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチの原理
■1636年 Rene Descartes (レーン・デカルト)
水の入った筒を眼に接触させると、見え方が変わることを指摘しております。
筒の長さをどんどん短くしていけば、現在のコンタクトレンズになります。

レーン・デカルト デカルトの原理
■1888年 A.Eugen Fick(オーゲン・フィック)
強角膜レンズと呼ばれるたいへん大きなレンズを、近視である自分の眼で実験して矯正を試みました。
装用感が悪く短時間で充血してしまったそうです。
“Eine kontactbrille”という本に記載されているkontactbrilleから現在のコンタクトレンズという名前ができました。
■日本初は (1950年)
当時名古屋大学の講師であった水谷豊先生が、角膜が突出してくる「円錐角膜」の高校生(視力右0.02、左0.04)にPMMA製のレンズを作成し、右0.9左0.4までに回復させることに成功しました。
PMMAハードレンズが普及するにつれていくつかの問題が明らかになってきました。
主な問題は、装用になれるまでに時間がかかること、1日の装用時間に限界があること、いろいろな自覚症状があり、装用できない場合もあること、無理な装用により角膜障害が生じること等であり、これらの問題の主原因は、HCLのPMMA素材が角膜の代謝に必要な酸素を全然透過しないためであることが判明しております。
引用:北村眼科
現在ではさらに進化して、目に負担の少ないソフトコンタクトレンズ。
そして、常に目を清潔に保てる1Dayの使い捨てコンタクトレンズが低価格で手に入ります。
これからは現在日常的に使われているものの機能を大きく進化させた道具が色々と開発され、世の中に出回りそうで楽しみです。
ありがとうございます。