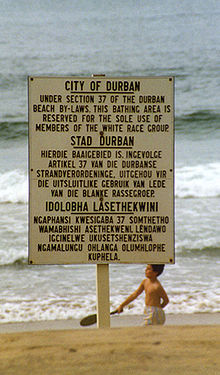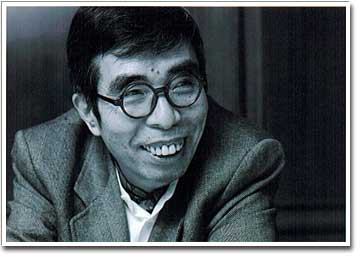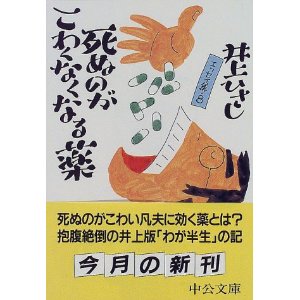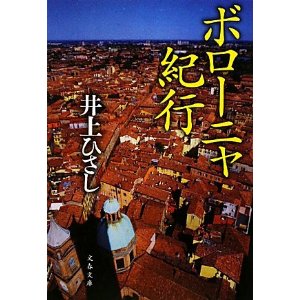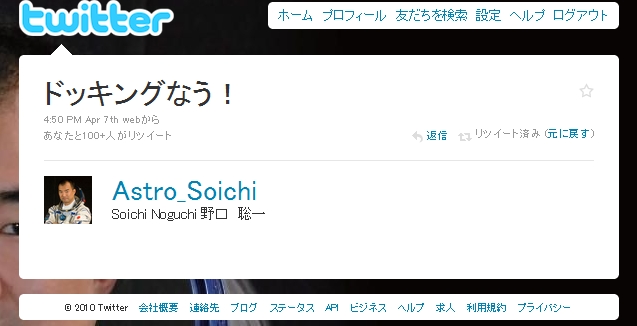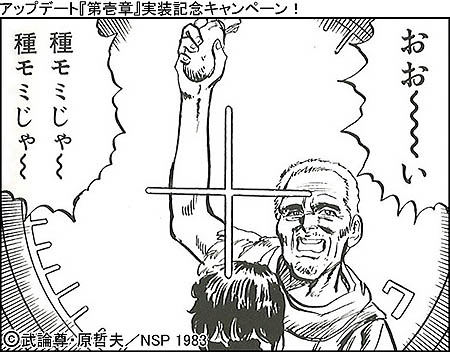HOME >
南アフリカ共和国におけるワールドカップ開催について。
2010.06.10|iwamura
さて、南アでのワールドカップ開催について、やれ治安がどうだとか、各種タブロイド誌が書き連ねているのを目にするが、まあハッキリ言って、残念である。
世界が一つになるイベントを前にし、水を差すようなことを言いすぎてはイカン(インフォメーションの域を超えたネタ報道にするなとだけ言っておく)。
さて、南アワールドカップと言えば、もちろん明日11日開始の大イベントであるが、当ブログにおいては、1995年に開催された南アワールドカップにも注目したい。
ラグビーのワールドカップです。優勝国は、開催国、南アでした。
30代の小生は、中学時代の歴史、地理において、「アパルトヘイト」という言葉を習いました。
南アにおけるネイティヴは、ビーチでもバスでも、至るところで隔離されていた時代がリアルにありました。
1989年ごろのダーバン市内の海岸で掲示された非白人立ち入り禁止の看板。英語、アフリカーンス語、ズールー語で併記
撮影・提供:John Mullen
中学生時代の小生は衝撃を受けるとともに、当時貿易を積極的に行っていた日本国民が「名誉白人」という不名誉な栄誉を与えられていることに関しても、フクザツに気持ちが悪く、申し訳がなかった。
しかし、1994年、民主活動指導者だった、「ネルソン・マンデラ」氏が、30年の牢獄生活から抜け出し、選挙にてネイティヴ初の大統領に選出されました。
当時は丁度ワールドカップ前年。南アはもともとラグビーは強かったのですが、白人たち主導による「スプリングボクス」というチームがあったんですね。アパルトヘイト時代の国旗そのままのユニフォームデザイン。
もちろん、ネイティヴは猛反対。「スプリングボクスなんか撤廃だ!」「人種差別の象徴を残すな!」
当然の論理。
でも、マンデラ大統領、チームの存続を決定します。ユニフォームも代えない。
「白人の愛するものを奪ってはならない。彼らはもはや敵ではない。仲間である。彼らを許し、今は、国を一つにする時なのだ。国を一つにする為には、奇跡(優勝)が必要だ。」
彼の掲げたスローガン。
「ONE TEAM ONE COUNTRY」
そして、奇跡は起こります。
上記「インビクタス~負けざる者たち~」監督はクリント・イーストウッド。主演はモーガン・フリーマン(ネルソン・マンデラ大統領)。ミリオンダラー・ベイビーの黄金コンビ、戻ってきました!
昨今のイーストウッドさんは、硫黄島といい、グラン・トリノといい、いい映画をつくるなあ。
インビクタス、見逃した諸氏へ朗報、7月11日DVD発売です。
「国家」「努力」「友情」「スポーツ」「勝利」「ドキュメンタリー」
人類にとってロマンチックな要素が満載の映画です。涙が、止まらなかった。
サッカーワールドカップに合わせ、南アフリカ共和国に思いを馳せてみるのもよいでしょう。
そして、今いろいろドタバタしている「俺たちの国家」も、今回のワールドカップで、一つになれたらいいな、と思っています。
ミニカーの思ひ出
2010.06.02|shiozawa
基本的にこれから「来そう」なものを取り上げる当ブログにおきまして、
約一名世の流れを遡上しまくるumiushiです。
出張後二回目の登場でございますが、先日武者ガンダムを買うべく、おもちゃ屋に行ってまいりました。
結論から申し上げるとほぼ100%経済的理由で諸般の事情でガンダムは買わなかったのですが、ふと別の棚が目に入りました。

これ
自分の小さなころ、もしくはお子様のいらっしゃる方なら息子さんのためにと、見おぼえがある陳列棚ではないでしょうか。
言わずと知れたベストセラー「トミカ」でございます。
ただ、車種が新しそうなのに、通し番号が意外に若いので不思議だったのですが、
「TOMICA」(トミカ)は、日本のメーカー「タカラトミー」が
製造しているミニカーです。トミカは同じ番号で、多くの車種が存在します。
ある期間製造され、型が古くなったりすると、
新たな車種を同じ番号で製作するためです。TOMICAとは? (Lovely MINICARs さん内ページ)
だそうです。ラインナップはいつも更新されてるんですね。
公式サイトによれば、


スバルインプレッサや、渋いところでは光岡のオロチまで発売中ですが、
の大好きなわたくしのこと、


ブルドーザーだのロードローラーだの
ばかり大人買い。しかし白眉は
農民の末裔としては買っておかねばなるまい。
——————————
そんなわけで我が家のテーブル上は、にわかに工事現場と化してしまいました。
これ、楽しい。
子供のためとトミカのミニカーを買い漁る。しかしミニカーを前にした時の瞳の輝きから、自分のために買っているんじゃないかという疑惑あり。
というエピソードも頷けるな。
トミカは本当に安いですし、まずは手に取ってみるだけでもうれしくなれますよ。
新入社員の"スパルタ研修"に批判 /「王将の国から~2010『絆』」
2010.05.04|iwamura
下記も見てみたが、別に批判するほどのことじゃねえよな、というのが小生の正直な感想なのだが、いかがなものだろうか?
(※一方確かに、やずやさんはやってしまった感が強いが。)
過酷な新入社員研修の様子がテレビで放送され、「ブラックすぎる」などと批判されていた「餃子の王将」の王将フードサービスがサイト上に釈明文を掲載した。
2010年4月11日、情報番組「TheサンデーNEXT」(日本テレビ系)で、同社新入社員研修の様子が放送された。
研修では、ことあるごとに怒号が飛び交う――。■スピーチで絶叫、涙流して抱き合う
その中でも特に強烈なのが、3分間の「私の抱負」スピーチだ。他の社員の前で「私の抱負は1年後チーフになり、店長になることです。絶対になります!」などと絶叫。「70点 合格!」と言われ、最後には役員と涙を流して抱き合う。まるで自己啓発セミナーのようだ。
同社は放送後しばらくしてから、サイト上に「弊社新入社員研修について」
という釈明文を掲載した。
■今の若者には「感謝を知ること」を一番教えたい
「現代の若者」は、家庭や学校でこうした躾をされることが少なく、叱られたことのない
人も多い。そのため、「通り一遍の無難な研修だけでは、学生気分から脱却させることはできません」というのだ。▽J-CASTニュース
http://www.j-cast.com/2010/04/27065521.html?p=all
小生の周りには、国の組織に属する人間もいるが、彼の会社も、炎天下で倒れるまで「気をつけ」とか、「六法全書で頭をブン殴られる」等、かなりハードコアな都市伝説を持つ。
また、「組織」として動く場合、弱い部分があると、そこから「抜かれる(突破される)」ことが最も恐ろしいのだ、という表現も、彼は使っていた。
「命掛けの最前線で、抜かれるわけにはいかないのだ。仲間の全滅に繋がる。」とは彼の弁。
「それされないように、仲間で助け合うのが『絆』だろ?」とも。
即戦力として現場配置された際、彼のところの新人君が仮に「抜か」れ、もし、彼の組織が全滅するとどうなるか。
それは
「(彼の組織がサービスを提供する)皆さんの生活に、モロに迷惑がかかってしまう!」
というゆゆしき事態に直結するのだ。新人が「抜か」れることは許されないのだ。
※2008年彼の会社の記念式典より
———————————————————————————————-
翻って、餃子の王将さんも、それは一緒ではないのか?「学生気分から抜け出させる」ってそういうことだと思う。
キッチンでは火も使うし、王将さんの扱う「食」とは、そもそも我々の「命」と直結する仕事である。現場配置が1年目だろうが10年目だろうが、お客さんにとってみたら「うまくて安い餃子(や定食)の安心な提供」がすべてであって、新人とかそんなもの知らん。うまいもの安全に食わせろ。であるはずだ。
「効率的な『組織の一員化』」
=即戦力
=「組織」としての顧客サービス安定供給
だとすれば、王将さんの方法は、当然「是」であると、小生の目には映る。
想えば、小生も新社会人1ヶ月目、初日から終電、タクシー、泊まりの繰り返しであった(涙)。GW明け、北海道へ1人で1週間出張し、最終日旭川のホテルで眩暈の為、ベッドから起き上がれず、昼過ぎまで「組織の為に」ウンウン唸っていたことを思い出す。
有難いと思っています。私はあのとき、強くなれた。
———————————————————————————————-
そして本日は、そんなスパルタ元上司も参列してくれる、私の人生の記念式典がございます(笑)。
「憲法を変えて戦争へ行こう!!
2010.04.17|iwamura
という、これは本のタイトルなのであるよな。この辺からも、井上ひさしさんのアソビゴコロが見えて好きなのだ。
井上ひさしさん、尊敬していました。大好きでした。
しばらく、筆が取れない話題であった。
「吉里吉里人」など奇抜な設定と軽妙なタッチの小説や戯曲、エッセーで知られ、護憲運動にも力を注いだ作家・劇作家で文化功労者の井上ひさし(いのうえ・ひさし、本名廈=ひさし)さんが9日、死去した。75歳だった。
※時事.comより抜粋
奇抜な設定と軽妙なタッチか。。。別に奇抜だとは思わんけどな。
しかし、「ひょっこりひょうたん島」なんて、だいぶセンセーショナルで、日本のコメディというか、テレビの泣き笑いの元祖は、このひとではなかったか。
おちゃらけていらっしゃるようで、国語の教科書を読むような、(読み手に対する)優しい敬語と、美しい日本語を書かれる方でした。
そもそも、戯曲家(劇作家。舞台の台本やテレビの台本も描く人。)という方々は、日本語のうまい方、読んでいてイメージが湧きやすい文章を書かれる方が多い。
小生の友人にThe New York Timesに記事を書くような男がおるのだが、彼はやはりホンを書く向田邦子さんを「天才」であると尊敬し、神がもし、なんでも願いをひとつだけ叶えてくれるなら、という問いに対して「美しい文章を書く才能が欲しい」と、のたまったことがある。しかしそれは、小生も同感であって。
井上さんの著書から覗いてみよう。美しい文章を書くためにはどうすればよいか。
「現在望み得る最上かつ最良の文章向上法とは」
ひとことですむ。こうである。
「丸谷才一の『文章読本』を読め」
とくに、第二章「名文を読め」と第三章「ちょっと気取って書け」の二つの章を繰り返して読むがよろしい。
以上で言いたいことをすべて言い終えた。あとは読者諸賢の健闘を祈る。
・・・・
まだだいぶ紙幅が残っている。そこであまり役に立ちそうもないけれど、一つだけ書きつけておくことにしよう。
「むやみやたらに文章を読むことが肝要」である。優れた文章家は、ほとんど例外なく猛烈な読書家である。どうかその真似をしてほしい。いい文章を書こうとする前に、感心な読書家になるのだ。
※井上ひさし「死ぬのがこわくなくなる薬」より抜粋
これは、勇気のもらえる文章だ。
いい読書家は、いい作家になれる。いい視聴者は、いいミュージシャンになれる。いい美食家は、いい料理人になれる。いい部下は、いいリーダーになれる。
「好きこそものの上手なれ。」小生は、苦しくなるといつも井上さんのエッセイを読んでいた。
昨今ではこれが良かった。
キリスト教の洗礼も受け、イタリアに暮らしたこともある井上さんが、その愛の全てをこめて書いたボローニャ礼賛の書。
ちょっと目次を抜粋してみましょうか。
・テストーニの鞄
・大泥棒とこそ泥
・そのとき、坊やは、背後から撃たれた
・花畑という名の都市
・二つのイタリア
このネーミングの妙と申しますか、ブログも、本も、タイトルが全てだと小生は思っているのだが、もうこの目次タイトルのつけ方からして天才的。
良かったですこの本。「イタリアなんてカッコつけやがって。絶対行くかばーか。」と思っていた小生は、HISでイタリアのカタログをもらってきてしまった勢いである。
この本は、イタリア人は国なんて信用してないけれども、自分の住んでいる街を愛し、大事にしている、という内容だったんだよな。「イタリア愛してる人」の文章だったなって。
井上さんは、(日本の本も)20万冊以上も所蔵し、美しい日本語で文章を書く人だった。だから、憲法9条にも固執した。この緑滴る美しい国日本を、国民を、愛し信じていた。
敗戦(東京裁判3部作)や原爆(父と暮らせば)と言う日本人の、人類の悲しみを表現してきた彼。そんな歴史を繰り返さないための、彼の遺言、最後に、記載しておく必要がありそうですね。
九条は戦争ふせぐ最良の方法 井上ひさし(劇作家)
ちかごろ、この第九条の中身が古いという人たちがいます。「平和主義」という考え方は古いでしょうか。問題が起こっても、戦争をせず、話し合いを重ねて解決していく。その考え方が古くなったとは、私にはけっして思えません。むしろ、このやり方はこれからの人類にとっての課題ですから、第九条は、新しいものだといっていい。日本は正しいことを、ほかの国より先に行っているのです。「平和主義」という考え方は、人類にとっての理想的な未来を先取りしたものだといえます。
先日のロイター村本さんも、「撃ち合いなんて、人間は本能的にイヤだろ!平和がいいに決まってるだろ!」っていうことを、できるだけ多くの人に伝えるべくして、ぎりぎりまで現場に踏みとどまってらっしゃたんだと思う。
賛否はあるでしょうが、彼の「最後の映像」もアップし、本日、日本と平和を考える、週末としたいと思います。
日本国憲法第9条 条文
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
宇宙開発事業と幸福論~はやぶさ動画より学ぶ~
2010.04.10|iwamura
と、いうことで、今週はドッキングもありましたね。
今国際宇宙ステーションには2人の日本人が行っています。ぼくら子どものころは信じられなかったな。
(※しかし相変わらず野口さんの毎日の写真いいよな。)
事業仕訳の関係で、宇宙開発予算がガッチリ削られました。
いたし方ないことではあると思う。理想や未来よりも、パンが大事な時もある。
それでもやっぱり、宇宙ステーションに2人も(もちろんnasaやjaxaも狙ってやっているんだろうけれども)送りだしている日本のような技術大国の責務は、日経新聞社説に言われるまでもなく、腹が減っても米百俵であり、未来の種モミを食ってしまうだけではいかんと思うのだ。
※このじいちゃんやられちゃうんだよな(「北斗の拳」より)。
6月に、2003年に打ち上げられた人工衛星「はやぶさ」が地球に帰還します。7年かけて、小惑星ITOKAWAから物質サンプルを持ち帰ることを目的としています。
この「はやぶさ」。何度もぶっこわれて、何度も通信が途絶えて、「さすがにもうだめかも!」を繰り返しつつ、しかしそのたびに奇跡の(計算された)復活を遂げて地球周回2万キロ軌道に入りました。
その過程を描いた以下動画。これは熱すぎる出来だ!(1分過ぎからトラブル続出)
真田△(さなださんかっけー)!「こんなこともあろうかと!」これはトリハダだなー何度見ても。
※しかも先日発表されたjaxaの再突入計画書がめちゃくちゃカッコいいので、これは企画書サンプルとして保存しちゃってください!ムダがない!
———————————————————————————————
人間の共通の幸福感について考えることがあります。
それって「達成感」であり、その達成感を得るための「未来を見据えた努力の過程そのもの」ではないか。
サンプルの有無ではない、事業仕訳なんかでは全然ない。今苦しくても、未来を考え、挑戦し続ける過程が宇宙開発事業であって、人生であり、人類のあゆみそのものではないのか。
幸せの為に生きるのではなく、未来を見据え、困難を乗り越え生きることそのものが、幸福であると私は考えます。
はやぶさにはサンプルが積まれていると信じますし、これからの日本の、宇宙開発事業の未来も、私は信じたいと思います。
「ケッ そんなところに まいたって みのるわけねえだろ」
「みのるさ…。下に あの老人が 眠っている」