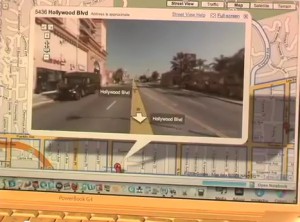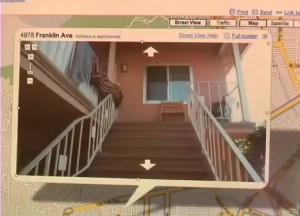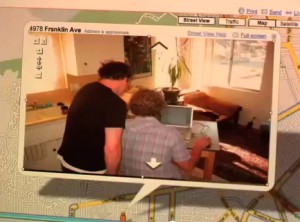HOME >
Google、iOSアプリの「Chrome」と「Google Drive」がついに登場!
2012.06.30|saito
こんにちわ!
齋藤です。
iPhoneユーザーでgoogleユーザーな方に吉報です。
Google、iOSアプリの「Chrome」と「Google Drive」をリリース
米Googleは6月28日(現地時間)、開催中の年次開発者会議「Google I/O 2012」において、
米AppleのiPhoneおよびiPad向けWebブラウザ「Chrome」とクラウドストレージ「Google Drive」を発表した。
両アプリとも既にApp Storeで公開済みだ。
デスクトップPCとしてはWindowsマシンを使い、スマートフォンやタブレットはiOS端末、
というユーザーにとっては待望のアプリだ。
google chromeの便利ポイントとしては、ブックマークをアカウント管理しており、
別端末でも同期可能だったり、ブックマークの種類が豊富なところが個人的には嬉しいところ、
このアプリを使う事により、iPhoneなどでも共有できるのは、ものすごい便利☆
また、chromの特徴でもある複数ページを表示した時の切り替え方法が端末により異なっており、
iPhoneとiPod touchでは切り替えボタンで、iPadの場合はスワイプでページを切り替えることができるとのこと。
Google Drive
Google Driveは4月に発表されたクラウドストレージサービス。
5Gバイトまで無料で、他の端末(Windows PC、Mac、Android)とファイルを共有できる。
また、対応するアプリが端末にインストールされていれば、Google Drive内のファイルを編集することも可能だ。
これまでもiOS端末のSafari経由でGoogle Driveにアクセスすることはできたが、
ネイティブアプリが登場したことでAndroidとほぼ同等の機能を利用できるようになった。
こちらは、以前のブログでちょこっと紹介をしたgoogleのオンラインクラウドストレージサービス。
取引先の方の中にも早速社内ストレージとして、活用しているところもあり、
かなりクォリティの高いクラウドストレージです。
これもアプリが出た事により、Androidとほぼ同等になったのは、心強いのではないでしょうか?
どんどん進化するアプリ業界!
今後も目が離せなませんね!
最後に、もうほんと「台湾」大好きだわ!となってしまうほど、心温まるニュースがあったので、ご紹介☆
台湾製パソコン基板、小さな字で「日本に神のご加護を」
先日、フェイスブックの会員の間で反響を呼んだ1枚の写真があった。写真は何の変哲もないただのパソコン基板。
だがよく見ると小さな字で「God Bless Japan(日本に神のご加護を)」と祈りの言葉が印刷してあったのだ。
基板とはパソコン内部に装填(そうてん)されている主要部品で、普段はまったくユーザーの目に触れることはない。
そこに日本への思いやりのメッセージがあった。 会員からは次々と「ありがとう。感激です」「感動した」など感謝のコメントが書き込まれた。同時に、いったい誰が、何のために、パソコンの内部基板にこのようなメッセージを印字したのだろうかと、大きな話題となった。
「日本に神のご加護を」と印字された基板を搭載したパソコンを製造したのは台湾のASUSで、同社も日本から問い合わせがあるまではこの事実を認知していなかったようだ。ASUSによれば、印字は同社の技術者が独断で行ったことで、誰かは特定できていないがたぶん日本の一日も早い復興を祈ってやったのだろうとのことで、本件は黙認しているそうだ。
一人の台湾人技術者が独断で思いつき、会社の許可も得ずに印字した日本の復興を祈るメッセージが、マスコミではなくソーシャルメディアを通して日本人の心を揺さぶった。「神のご加護を」は日本では一般的な言葉ではないが、英語圏では最もなじみの深いフレーズの一つで、God Bless JapanのスローガンはTシャツやポスターのデザインとなり、Pray For Japan(日本のために祈ろう)とともに世界中で東日本大震災の義援金集めの標語となった。
涙出そうです。。。。
自分ももっとお客様に幸せになってもらえるような仕事をしようと、改めて考えさせられました!
ありがとうございます!
Google mapに気を付けて(ネタ)
2012.05.27|saito
こんにちわ!
齋藤です。
日曜日です。
昨日は、ちょっと真面目に書いたので、今回はネタで勝負です!
いつも何気なく使っている「google map」ストリートビューができて、だいぶ話題になっていましたが、
今では何気なく使用していると思います。
以前は、googleサイドで、こんなネタモノもありましたね
【エイプリルフール】Googleマップがドラクエ風に!?【2012.04.01】
しかし、そんな「google map」が、もしもこんなだったら怖すぎるという動画がyoutubeにあがっていたので、
ご紹介~。
いつもの調子で、google mapをやっています。
家の近くを検索♪
近づいてきました。
ん?家の階段までいけるのか?
この部屋って。。。
この後姿は、自分達?
振り返ってみると。。。。
怖っ!!
なんかこんな怪談があった気がする。。。
最後にどうなったかご自分の目でご確認下さい。
Google Maps (Part I of “The Googling”)
齋藤でした~
「ありがとう、スカイツリー」 一日限りの夢舞台、解体始まる
2012.05.24|iwamura

22日に開業した東京スカイツリー(東京都墨田区、高さ634メートル)の解体式が23日早朝から行われ、総事業費650億円をかけた一日限りの夢舞台に幕を閉じた。今後は13年2月をめどに解体工事を完了し、翌14年1月から、同じく高さ634メートルの「東京スカイツリー2(仮称)」の建設に取り掛かる。
スカイツリーの運営会社である株式会社東京スカイツリー634では、目新しさを前面に押し出した「スカイツリー特需」を維持するためには、今後も永続的に解体と建設を繰り返す「スクラップ・アンド・ビルド」方式(【用語解説】参照)を採用することが最良と判断。開業翌日となる23日からさっそくタワーの解体作業に着手した。解体が終わり次第、再び同じ場所に今度は「東京スカイツリー2(仮称)」を建設する。
東京スカイツリーに入るため、朝4時から並んでいたという29歳の男性は「今日なら中に入れると思ったのに…」と話し、次々と解体されていくスカイツリーの残骸をぼう然と見つめていた。
【用語解説】:「スクラップ・アンド・ビルド」
人気のなくなった店舗をいったん閉店し、同じ場所に新店舗を立ち上げることで消費者からの注目を集める手法。うちの近所にある紳士服のはるやまが「完全閉店セール」「新装開店セール」と称してよくやっている。
※虚構新聞より
ということで、虚構新聞相変わらずイケイケで笑いました。
あっぱれだと思うわけです。
先日、例の大阪は橋下市長の「小中学校におけるtwitter義務化」の記事掲載時に、一部炎上(?)というオカシナ顛末にて物議をかもした虚構新聞ですが、やはりというかトーゼンと申しますか、「ネタはネタ」なわけです。
虚構新聞の「そもそも悪ふざけが過ぎる」という炎上問題に関しては、諸処の意見展開がなされており、それを我らがやまもといちろうセンセイがまとめられた文書がございますのでそちら抜粋し、恥ずかしながら自分の個人的感想も含め、下記に記しておきます。

1)メディアを面白くなくさせる奴等
http://www.nurs.or.jp/~ogochan/essay/archives/3789「ちょっと調べれば虚構新聞だと分かるんだから、つまらんケチつけてねえで騙された奴は素直に反省しとけボケ」というお立場であります。一理ありますね。
いわゆる「あたりまえ」な論理。「クリックを惜しんだのはお前だ」。
2)虚構新聞騒動に見る「弱者の論理という狂気」
http://togetter.com/li/304472Togetterからは、加藤AZUKIさんをピックアップ。騙された馬鹿を弱者と見立てて華麗に立論している点がかなり秀逸で、上記おごちゃんとはまた別の立脚点となっていて興味深いわけです。ジョークを事実だと思い込んだ弱者の権利主張によって、ジョークを言う側が格別の配慮をしなくてはならなくなった、という、いわゆる「有名になるということは馬鹿に見つかるということ」という立論に近い、味わい深い議論です。
「ジョークを笑えないのは野暮」この一言につきますね。
3)虚構新聞に関してポジショントークする人々の16種類の本音
http://ulog.cc/a/fromdusktildawn/17450ご自身も、是非自分のポジを確認してみてください。なお、私のポジションは(1)と(3)です。
自分も(1)と(3)ですね。
4)虚構新聞は風刺サイトじゃないよね
http://d.hatena.ne.jp/NOV1975/20120516/p1確かに実在の人物が言いそうなことを捏造して面白記事に仕上げているわけですから、少し調べれば分かるだろ的な議論に対する有力な反論として成立しており、相変わらず立論がしっかりしているなと思うわけです。
う~ん、個人的にはチガウかなあ。風刺サイトじゃないというか、「ネタサイト」でしょ。
5)[WEB][雑記]『虚構新聞』とネットリテラシーの限界
http://d.hatena.ne.jp/fujipon/20120516#p1つまり、騙される人も騙されないようになっていく過程であり笑うべきではない、騙されない人は騙された結果の反省として前に立っているので怒るべきではない、という、そういうグレーゾーンの外角低めにストレートを投げ込んだ虚構新聞は「耐性をつけるための雑菌であり、必要悪」的なアプローチで締めています。必読です。
「twitterは義務化すべきかもしれませんよ。虚構じゃなくて。」に全てが集約されておりますね。
6)虚構新聞社主の悲しい勘違いによる主張をはい論破
http://anond.hatelabo.jp/20120517123355匿名ダイアリーからはこんな議論が。昔からあるテキストサイト文化を引きずって、ネットだからネタで許される時代ではないのだ、文明開化せよ、というごもっともな主張であります。
ごもっともではありつつも、そんなアオスジ立てるようなハナシかいな。というところが小生のホンネ。
7)「虚構新聞」の事を語る前に、まず「東北大学助教授レポート」の件を考えようよ
http://damedesu-orz.org/kimlla/archives/site/201205162222.htmlもともと、ジョークのつもりで書いた話がネットの中で一人歩きして、さも事実であるかのように定着してしまうことの恐ろしさを、一時期話題になった「東北大学助教授レポート」ネタを例に立論しています。
筆者自らが「世知辛いことよ」と書いている通り、ウェブが一般化したことによって、とても窮屈になり、この程度のジョークですらも自粛しなければいけないほど批判されうるのか、という締めも素晴らしいです。
同感ですね。。。
8)虚構新聞の件をデマ扱いするのは納得できないというお話
http://d.hatena.ne.jp/itotto/20120516/1337187664問題を虚構新聞そのものと、騙された馬鹿に分けて立論していき、最終的にはガセネタを流されて迷惑する形となった橋下さんがどう考えるのか次第だ、という落ち着きどころに綺麗に着地しています。
1.ウソと言いつつあまりにリアリティがあり過ぎた
2.ネタのチョイスに失敗した
3.サイトを目にする人の層が変わってきた
「だからこその100点!」だと思うんですけれども。
9)[その他]虚構新聞だからデマでも許されますって思ってる奴今すぐ死ね
http://d.hatena.ne.jp/kyoumoe/20120515/1337015051こちらも率直に「虚構新聞がデマを流して許されるわけねーだろ」という立論でありまして、これの派生はさまざまあれども基本はこちらの考え方がベースになろうかと思います。
まあ、ネタとして面白い主張ではありますね。
10)いい加減、虚構新聞はタイトルに虚構新聞だと明記しろ
http://n-styles.com/main/archives/2012/05/15-050000.php「『電子レンジを猫の乾燥に使わないでください』という注意書きと同じレベル」に対し「私の要望は『電子レンジの箱には、電子レンジと書いて欲しい』」というのは、実にエッジの立った議論だな、と思います。
これもネタとしては秀逸でございます!
11)虚構新聞は誰でもなくインターネットに殺された。
http://anond.hatelabo.jp/20120516180543さらに、この匿名ダイアリーではガセネタの一人歩きから、いわゆる2ちゃんねるまとめ系サイトのソースロンダリングにまで踏み込んで、馬鹿を釣る仕掛けとしての強いタイトルがネットの情報流通に悪しき影響を及ぼしている、という認識を綺麗に展開しています。ごもっともですね。
わかりますが、そこまでのハナシなのかなーぷぷぷ、というのが正直なトコロ。
12)なんか、また釣られた人が吠えているようだけど
http://d.hatena.ne.jp/tonan/20120515#p1tonan氏の議論もまた、オーソドックスな「ソースは確認するべき」という原理原則に立ち返っての立論でもあり、一方で信頼性の低そうなタイトルを引用してTwitterなどで拡散する人そのものの問題も置き去りにしないほうが良いのではないか、というテーマを、あまりにも象徴的な東スポを使って論じています。
※以上やまもといちろうブログより
東スポ(笑)。ナイス切り口であります!
—————————————————————————————————
と、いうワケで、皆様ご意見はいかがでございましょうか。
小生の論点を簡潔にまとめさせて頂けるとすれば
「ここまでの議論をネット上に爆発させた虚構新聞は最高です!」
とするものであり、上記ド炎上のちに
「さらにスカイツリー解体ネタをかぶせるあたり、タイミングも含め秀逸!」
という拍手ぱちぱち以外の何ものでもない、ナイスネタウェブサイトであると思います。
怒っていらっしゃるご仁を玉露を呑みながら眺めることも含め、虚構新聞の影響力にあっぱれ。
今日も心で泣いて、でも顔は笑って、がんばるひとでありたいものです。
~挑戦的なホンダのものづくり~ 電動1輪車”UNI-CUB”
2012.05.18|shiozawa
ホンダといえば、自動車ですが、当然車はタイヤが4つついてます。
ところが、ホンダはよりによってタイヤが1つの電動一輪車も開発しているようです。
名前は“UNI-CUB(ユニカブ)”。
■ホンダ、補助輪付き電動1輪車「ユニカブ」の実証実験
ホンダは2012年5月15日、1人乗りの補助輪付き電動1輪車「UNI-CUB(ユニカブ)」を開発し、6月から実証実験を始めると発表した。
体重移動に伴う座面の傾きや速さに応じて、前後左右の移動に加えて旋回できる。
歩く速さと同じくらいで最高速度は時速6km。屋内の段差が少ないバリアフリー空間での移動が対象。
ホンダが2009年に発表した電動1輪車「U3-X」の後継機となる。
実証実験は、東京都の日本科学未来館で実施する。「どのようなニーズがあるのか見極める」(本田技術研究所二輪R&Dセンター企画室主任研究員の末田健一氏)のが狙い。
引用:日経新聞
すごくかわいらしい形かつ、かわいらしい動きをしますね。
最初は一時期非常に注目されたセグウェイみたいな乗り物かなと思いましたが、大分違う動きをしてますし、乗り物というより“動く椅子”みたいで、これはこれで新しくて面白いです。
私がすごくこの商品の開発で好きなところは
挑戦的なものを作って、あとからニーズを見極める ところ。
“お客さんのニーズをとことん聞き出して、よりニーズに合ったものを製造する”のは、商売で大切なことですが、
その先の意外な新しいニーズを生み出すのは、今回紹介したUNI-CUB(ユニカブ)
のようなものなんじゃないかなとつよく感じます。
「そんなもの必要かー?」と思えるような挑戦的なものを作って、後から“こんな使え方までできちゃうんだー”とあとから生まれる発見が大きな感動を呼んだりもするのかなと。
このユニカブのほかにもホンダの最近ホットなのがあります。
久しぶりの国産飛行機“ホンダジェット”。
■ホンダジェットの飛行試験用量産型4号機、初飛行に成功
ホンダの航空機事業子会社のホンダ エアクラフト カンパニー(HACI)は13日、小型ビジネスジェット機『ホンダジェット』の飛行試験用量産型4号機が米国ノースカロライナ州で初飛行に成功したことを発表した。
量産型4号機は、米国東部時間5月4日10時57分に米国ノースカロライナ州のピードモントトライアッド国際空港を離陸。高度1万1500フィート(約3500m)を速度313ノット(時速約580km)で順調に飛行した。
今回の74分におよぶ飛行試験では、降着装置や高揚力装置などの機能試験、機体の基本性能や操縦安定性、データシステムや計器着陸システムの確認試験などを行った。
引用:日経新聞
今回開発された“ホンダジェット”はかなりの自信作のようで
「HondaJetは、客室(キャビン)内の広さ、燃費の良さ、飛行可能な速度のすべてで既存の小型ビジネスジェット機に勝っている」。
米Honda Aircraft社の社長兼CEO(最高経営責任者)の藤野道格氏は、HondaJetの競争力の高さについて自信を見せる。
引用:日経新聞
とのこと。
エンジニアだってセールスマンだって、革新的な他社に絶対負けないようなものを作り、売れる事こそが仕事の楽しさだと思います。
こういった2歩先を行った商品開発への挑戦が創設者“本田宗一郎”のDNAなのでしょうか。
最近苦戦している日本の産業ですが、こういった攻めの姿勢が私たちに大きな勇気を与えてくれます。
ありがとうございます。
2chの件。
2012.05.17|iwamura
ということで、2chをめぐる昨今の騒ぎ(?)ですが、この辺に問題があるのだろうと。
2ちゃんねる、削除要請情報97%放置…3倍増 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120510-OYT1T00333.htm 2ちゃんねる:薬物は削除基準外 「管理甘い」指摘も http://mainichi.jp/select/news/20120510k0000e040207000c.html
。。。
ただ、「放置」していただけのことが、直ちに犯罪や薬物使用の「ほう助」にはならないんだろうなあ。
「削除なんてするなよ」と2ch側が逝って(指示して)いたならともかく。
あれだけのマンモス掲示板になると「管理人もあずかり知らないところで」っていうのもまた事実だと思われ。
しかし一方で、こっち(麻薬)のほうのはなしとあわせ、以前からちょいちょい議題に上っていた「ペット大好き掲示板」のほうでの問題について、2chをひろゆきさんと一緒に立ち上げた、我が敬愛するやまもといちろう先生がご意見展開しておられましたので拝見しに逝って参りました。

出かけ際に、読んでびっくり。なんぞこれ、と思ったのでピックアップ。
http://hiro.asks.jp/
http://megalodon.jp/2012-0516-1805-32/hiro.asks.jp/裁判所でないと判断できない、というのは文字通り合法か違法かであって、この合法違法の「違法」と、今回問題となる「違法情報」は違います。
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_illegal.html
違法情報そのものは、裁判所が違法と判断したものでなくても表示されている状態で削除しなければなりません。
公序良俗に反する情報も同じです。
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_morals.html
不作為で違法情報を削除をしなかったことで薬物特例法の幇助というのはどうなんだと思うところでありますので、この辺の線引きはむつかしいです。何しろ、薬物情報が掲載されて、削除されなくても罪に問われないというのはザル法もいいところであることを満天下に晒すことになるし、そもそも掲示板に公的なルールで削除を求めるルートが存在していなかった(削除依頼板という独自の方式で運用しているだけで良しとしていた)のは、悪しき先例になっちゃう可能性も強いわけですしねえ。
とりあえず「ちなみに、日本は、合法か違法かの判断は裁判所が行うことになってますので、財団法人が情報を違法と決めることは出来ません」とかいう法律解釈のままで走ってきたのは、以前、2ちゃんねるでの削除依頼の民事裁判で一定の結論が出ていることもあり、要はホットラインセンターから通達があろうなかろうと、
「違法情報を削除する義務は管理人にある」ってことを忘れているのでしょう。
くれぐれも、良い子は真似をしませんように。
—
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」に書き込まれた発言で名誉を傷つけられたとして、 東京都内の動物病院と経営する獣医師が管理人に500万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。久保内卓亞裁判長は400万円の支払いと書き込みの削除を命じた一審・東京地裁判決を支持し、管理人側の控訴を棄却した。問題となったのは、昨年1月以降、2ちゃんねるの「ペット大好き掲示板」内に匿名で書き込まれた「ヤブ医者」「動物実験」などの発言。
久保内裁判長は、一審判決と同様に「匿名の発言について、被害者が責任追及することは不可能だ。
削除できるのは管理人だけであり、他人の名誉を棄損する発言が書き込まれたときは、管理人には直ちに削除する義務がある」と述べた。http://www.asahi.com/national/update/1225/027.html
※やまもといちろうブログ「西村博之さんは、2004年の段階で知識が止まってしまっていたらしい…」より
ということで、「管理人側の控訴棄却」です。
強大な力を持つ「ひと」だったり、「システム」だったりには、もちろんその社会的な「貢献」や「素晴らしい部分」もたくさんある代わりに、悪い意味での「影響力」も強いわけで、それを「管理するひと」には一定の責務は発生するよな。。。とは思います。
もちろん、ひろゆきさんが設立した(?)「パケットモンスター社」がシンガポールにおけるダミー会社だとか、www.2ch.netの所有権がフィリピンの会社に移っているとか、実態が良くつかめないところも「アヤシイ」とされる一側面として見られてしまいがちなんでしょうけれども。
いずれにせよ、「最低限の管理」は管理者側が行うと同時に、我々ひとりひとりの2chユーザーも、やっぱりネタはいいとしても、根拠のないヒトの悪口とか書きすぎるのは控えましょう、というところですね。
一部2chでファンもいらっしゃる神田弁護士の所属司法事務所長とは懇意です。
こんど、また情報交換会(呑み)にて当問題については詰めてきたい所存です。