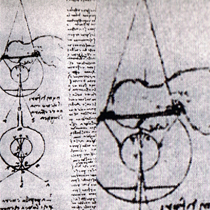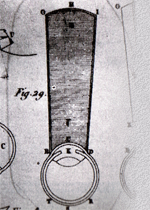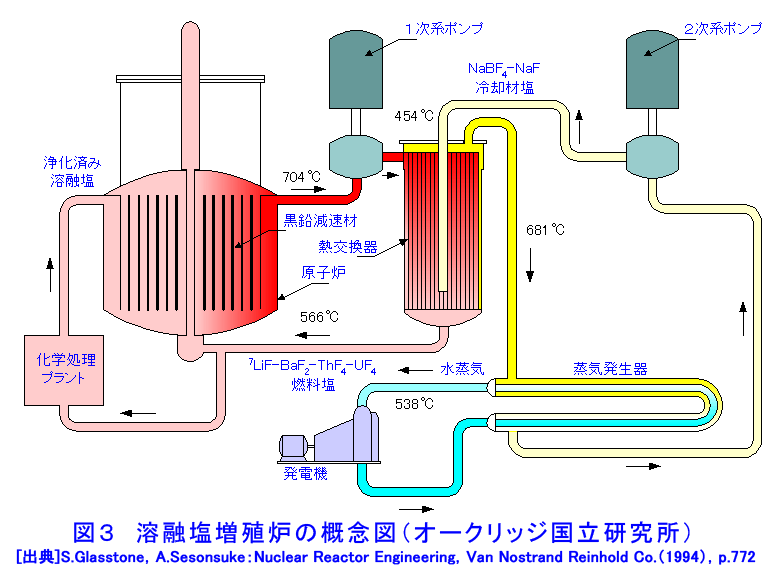HOME >
リニアモーターカーよりさらに高速な輸送システム構想
2013.07.19|shiozawa
未来の高速な輸送システムといえば
“リニアモーターカー”
を思い浮かべますが、アメリカではさらに高速な輸送システムを考えているようです。
■45分で米国横断:テスラCEOが構想する新輸送システム
SpaceX社やテスラモーターズのCEOを務める起業家イーロン・マスクは、
巨大な気送管の中でリニアモーターカーを走らせ、ロサンジェルスからニューヨークまで45分で人々を運ぶ未来を思い描いている。
北京までは2時間だ。
正気には聞こえないが、マスク氏が語っているのは1900年代から構想されてきた技術だ。
さらに、少なくとも1社が実際にプロトタイプを開発しようとしている。
マスク氏は7月15日、「新交通システムHyperloopの暫定デザインを8月12日までに発表する」とツイートした。
Hyperloopの具体的技術は現段階では明らかになっていないが、米国等のドライヴスルー銀行でお金が窓口係に吸い寄せられるような旧来型の気送管(エアシューター)システムに似ていると推測される(気送管は圧縮空気もしくは真空圧を利用して、管で電報などを輸送する手段。欧米では19世紀後半から利用された)。
引用:WIRED.jp
まず冒頭にとんでもなく高速な交通手段を実現したいと言っているのは
最近、火星移住化計画を発表し話題を集めたスペースX社の創設者でありCEOの
“イーロン・マスク(Elon Musk)”氏。
まだ42歳。なかなかお若いです。

まだ、正式な構想が発表されていないので、はっきりしたことは言えないのですが
真空管にする事で空気摩擦を限りなく0に近づけ、さらに
力を加える部分も超伝導(リニアモーター)により摩擦を限りなく0に近づける
といったもの。
これでブレーキになってしまう摩擦を極限まで減らすことによって高速化できるようです。
上の話でありました気送管(エアシューター)とはあまりなじみのないものですが、その歴史は古く
1850代に発明され多とのことで今より160年も昔からある技術のようです。
こちらがその初期1870年代の気送管
これは電報の運搬のために用いられいていました
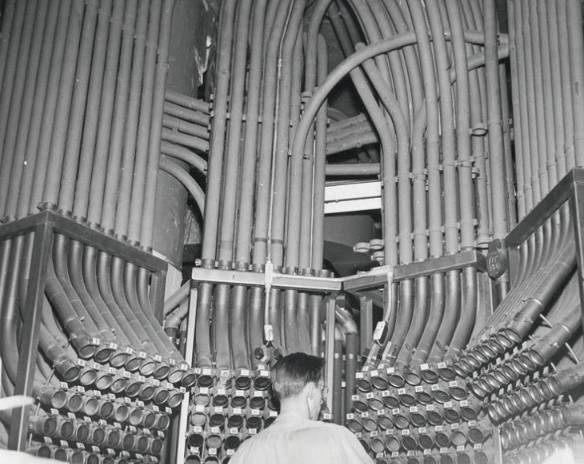

この方法に似た技術を使いかつ大型化して人が乗れるようにするとの事です。
コロラド州ロングモントにあるET3社は現在、
「地上の宇宙旅行」として、真空化チューブ内輸送機関(ETT)を開発している。
ETTでは、2本のチューブ(各方向に1本ずつ)と、重さ約180kgで乗用車サイズのカプセルを用いる。
カプセルは6人乗りで、それぞれがリニアモーターで加速する(冒頭の動画)。
ET3社によると、国内旅行だと平均スピードは時速約600km、国際旅行だと時速約6,400kmというとてつもない数字になるという。
(中国では最高時速4,000kmの「真空リニア」を研究中で、2020~2030年の実用化を目指していると報道されている)。
「真空チューブ列車」のコンセプトは、もともと1910年代の初めに浮上したものだ。
1972年にランド研究所が公開した、物理学者のR.M.ソルターによる「超高速輸送システム(VHST)」という論文では、ET3社が開発しているものにとてもよく似たものが説明されている。
マスク氏に近い情報筋によると同氏はET3社について、方向性はいいが鍵となるいくつかの要素が欠けていると述べたという。
そしてマスク氏自身は2社の経営で忙しいため、別の開発チームに関与するかたちを考えているという。
マスク氏はTwitter上で、Hyperloopをできるだけオープンソースで開発したいと述べた。
またパートナーについて聞かれ、「画期的な技術を迅速に、そして無駄遣いせずに実現するという思想的な目標を共有しなければならない」と述べている。
引用:WIRED.jp
中国の真空リニアやET3社が現在開発中のETTなど、技術も確立していませんし、若干胡散臭いところがありますが
今実現できないものを実現しようとする事こそが時代の進化を推し進めます。
まずは、イーロン・マスク氏が
Hyperloopのデザインを8月12日までに発表する
とのことなので、近日されるであろう発表が楽しみです。
ありがとうございます
最先端“望遠コンタクトレンズ”☆
2013.07.05|shiozawa
多くの人がごく日常的につけている“コンタクトレンズ”。
現在の製品でも、十分よく見えるようになりますし、値段も手ごろなんですが、
最先端技術のコンタクトレンズはプラスアルファですごい機能がついてきそうです。
■世界初! 倍率切替可能な「望遠コンタクトレンズ」
目に装着するだけで「望遠鏡」になる画期的なコンタクトレンズが開発された。
通常のコンタクトレンズと変わらない薄さで、通常視覚の約3倍もの望遠効果が得られるものだ。
加齢黄斑変性症の視覚補助器具としても実用化が期待されている。
左は「望遠コンタクトレンズ」の外観。
直径8mm、最大厚さ1.17mm。右は3D眼鏡と組み合わせた様子。
偏光フィルターによって中央の穴への光の入射を切り替える。
実はほかにも「望遠コンタクトレンズ」の開発は行われている。
しかしいままで開発されたものは4mm以上の厚みがあり、実用上の大きな課題になっていた。
今回新しく開発されたレンズは、最も厚い部分でも1.17mmしかない。
装着した際の違和感も小さく、実用化へ大きく近づいた。
この「望遠コンタクトレンズ」は、誰でも装着することができる。しかしこの技術を最も待ち望んでいるのは、加齢黄斑変性症患者だろう。
加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って網膜に異常が生じ、最悪の場合は失明にも至る疾患で、その患者数は全世界で増加している。iPS細胞の最初の臨床試験の対象としても話題となった疾患だ。
今回の「望遠コンタクトレンズ」は、加齢黄斑変性症患者にとって、心理的にも受け入れやすい視覚補助器具になると期待されている。
引用:Wired.jp
これはなかなかすごいです。
人には備わっていない望遠機能が今までのコンタクトレンズと同じように装着するだけでできてしまう。
本来の役割の“視力の補助器具”としての機能を完全に超えてます☆
バードウォッチングが望遠鏡や双眼鏡なしでできそうです。
また、軍事関係では特に使われそうな予感がします。
最先端もあれば、もちろん歴史もある。
ということでコンタクトレンズの500年の歴史をちょこっと紹介。
実は歴史はいがいと長いんですね。
<コンタクトレンズの歴史>
■1508年 Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ)
ルネッサンス時代、ガラスの壺に水を入れ、顔をつけて目を開けたところ、外の景色が変わった事からコンタクトレンズの原理が発見されたと言われています。
水を満たした球形の容器に眼をつけるイラストを使って、その視力矯正効果を論じています。
ダ・ヴィンチはコンタクトレンズの原理の創案者であると考えられております。

レオナルド・ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチの原理
■1636年 Rene Descartes (レーン・デカルト)
水の入った筒を眼に接触させると、見え方が変わることを指摘しております。
筒の長さをどんどん短くしていけば、現在のコンタクトレンズになります。

レーン・デカルト デカルトの原理
■1888年 A.Eugen Fick(オーゲン・フィック)
強角膜レンズと呼ばれるたいへん大きなレンズを、近視である自分の眼で実験して矯正を試みました。
装用感が悪く短時間で充血してしまったそうです。
“Eine kontactbrille”という本に記載されているkontactbrilleから現在のコンタクトレンズという名前ができました。
■日本初は (1950年)
当時名古屋大学の講師であった水谷豊先生が、角膜が突出してくる「円錐角膜」の高校生(視力右0.02、左0.04)にPMMA製のレンズを作成し、右0.9左0.4までに回復させることに成功しました。
PMMAハードレンズが普及するにつれていくつかの問題が明らかになってきました。
主な問題は、装用になれるまでに時間がかかること、1日の装用時間に限界があること、いろいろな自覚症状があり、装用できない場合もあること、無理な装用により角膜障害が生じること等であり、これらの問題の主原因は、HCLのPMMA素材が角膜の代謝に必要な酸素を全然透過しないためであることが判明しております。
引用:北村眼科
現在ではさらに進化して、目に負担の少ないソフトコンタクトレンズ。
そして、常に目を清潔に保てる1Dayの使い捨てコンタクトレンズが低価格で手に入ります。
これからは現在日常的に使われているものの機能を大きく進化させた道具が色々と開発され、世の中に出回りそうで楽しみです。
ありがとうございます。
NHKで開発されたさまざまな最新技術☆
2013.06.28|shiozawa
誰もが1度は見たことのあるNHKのドキュメンタリー映像。
世界中の動物や昆虫の生態を紹介したり、
世界中の絶景を絶妙なアングルで紹介したりと
まるで、自分が世界を旅しているかのように感じさてくれる映像の数々。
それは時代時代の最高技術で撮影された為。
そこで、今回はNHKが開発したすごい最新技術をご紹介。
<多視点ロボットカメラシステム(ぐるっとビジョン)>
動画を多くの視点で、しかもアングルを動かしながら撮影できる。
多視点映像の代表例といえば映画の“マトリックス”。

シーンの途中で突然映像が止まって、グルーッと180°アングルがかわる。
そんな映像シーンを見た時、少し驚いたのを覚えています。

この映画シーンの撮影の場合は一瞬を一気にカメラで撮影して実現していますが、
今回のNHKで開発された撮影技術では、
多視点を“動画でかつアングルを動かしながら”見られるということでさらに面白い。
家にあるテレビのコントローラで自分が見たいスポーツの名シーンをいろんなアングルで自由に動かしながら見られるようになったらとっても面白いなと感じます。
次に紹介するのも映像系。
<スーパーハイビジョン対応超小型カメラヘッドや世界初のHEVCリアルタイムエンコーダーを開発>
2013年の最新のデジタルハイビジョン機材ということ。
最新のテレビは4Kかと思ってましたが、早くも8K対応の映像が制作できる。
しかも、片手に乗るサイズのカメラであるから驚きです。
イメージ的にはこんな感じだったので
いかにコンパクト化しているかよくわかります。
次は
見るだけでなく“触る”感覚が得られる技術。
<仮想物体の輪郭をなぞる感覚を再現できる装置>
テレビに映っている映像を見るだけでなく肌で感じられます。
加えて“とがったものを触る感覚”も得られるとのこと。
現在はまだ指先のみしか感じられませんが、これが手のひらで感じられるようになればもっともっと映像が楽しめそうです。
昔、NHKで放送されており、最近でも深夜に再放送された事もあった
『NHK特集 シルクロード』

時代と世界が感じられる、最高のドキュメンタリー映像でした。
こういったものが最新の映像技術でまた新しく誕生するの楽しみにしています。
ありがとうございます。
中国の次世代原発研究“トリウム溶融塩炉”
2013.06.21|shiozawa
昨今も、“原発の存在意義”について騒がれる(特にテレビですが)ご時世です。
一般的に原子力発電といえば
“ウランを核分裂させて、その際に発生する膨大な熱エネルギーで発電するもの”です。
そんな原子力発電。
隣国の中国は最近“ウラン”ではなく
“トリウム”というあまり聞きなれない物質の原子力発電所を実現しようと急ピッチで研究しているようです。
その意図とは。
■中国、次世代原子炉の開発急ぐ 「トリウム」に脚光
エネルギー需要が増大する中国で、次世代原子炉を開発する動きが加速している。
ウランの代わりに、大量に余剰があり廃棄されてきたトリウムを燃料に使う「トリウム溶融塩炉」の研究が進む。
炉心溶融(メルトダウン)の危険がなく放射性廃棄物が少ないという。
日本も米国と協力して過去に同様の炉を研究しており、将来の選択肢に加えるべきとの指摘もある。
メルトダウンは原理的に起きず
「平均年齢30歳の若手を中心に約500人が次世代炉のプロジェクトを進めている」――。中国科学院上海応用物理研究所の徐洪杰TMSRセンター長は今年4月、都内で開いたシンポジウムで開発陣容の拡大を明らかにした。
引用:日経新聞
このトリウム溶融塩炉とやらは
メルトダウンする可能性がなくて、放射性物質の漏れがほとんどないということで、現在のウランの原発に比べて圧倒的に安全という事。
では、なぜ中国?ということですが、他にも事情があるようです。
TMSRはトリウム溶融塩炉の略。天然には原子番号90のトリウム232が存在する。
モナザイトと呼ばれる地球上に広く分布する鉱物から得られる。
レアアース(希土類)を採取した後の廃棄物に多く含まれる。中国のトリウム保有量は豊富で、国内の電力消費を数百年賄えるという。
自国にあるエネルギ‐を有効活用し、
将来発生するであろうエネルギー問題を早いうちに解決しようと国が主導(厳密には共産党)で行っている
いうことです。
それに比べて日本はどうでしょう?
まず、自然エネルギー発電で日本全体のエネルギー問題を解決することは不可能
だとわかっております(一応世界第3位のGDPの大きな国です)。
最近では
原発はほぼ停止し、化石燃料発電にほとんど頼り、そのコスト高のせいで発電所は毎年数兆円の膨大な赤字を出し続けています。
このままただひたすら赤字をし続けていても、国のエネルギー問題が解決するわけありません。
福井県にある“高速増殖炉「もんじゅ」”や

青森県六ヶ所村にある核燃料の再処理工場など

など、原子力系の研究も長年行っております。
たしかにいつ起こってもおかしくない将来発生するであろうエネルギー不足に備えて
研究は日々前進はしているようです(いろんな問題を抱えつつも)。
しかし、中国ほどの危機感と研究に対する勢いが感じないのが現状です。
ここで、ちょっと将来性を感じる研究結果がありましたのでご紹介。
■高速増殖炉「もんじゅ」が不要に?軽水炉で高増殖が可能に!核燃料サイクル実現へ (2013.01.05)
夢のような研究成果が発表された。
燃料棒の設計を変えただけで、原発軽水炉で、高速増殖が可能になるという。
これが、もし実現可能ならば、危険な金属ナトリウムも使わず、今まで処分の難しかった核燃料廃棄物が、中性子を吸収してPu239という燃料に変わる。
これにより、通常は85年程度で枯渇すると言われたウラン資源を100倍活用できる。素晴らしい研究成果である。
早稲田大学(早大)は12月26日、放射能の密封性を損なうことなく水対燃料体積比を低減できる、核燃料棒を隙間なく束ねた新燃料集合体を考案し、世界で初めて「軽水冷却原子炉による高増殖性能」を計算上ではあるが達成することに成功したと、同大大隈会館にて行われた会見にて発表した。
引用:連載.jp
こういった、将来性を感じる、素晴らしい研究結果も出ています。
また、中国が現在国を挙げて研究している“トリウム”の研究もかつて日本も盛んに研究されていた時代があったとの事です。
“原子力発電は危険だからダメだ”という、何も考えずに否定する事をせず
広い視野を持って、より安全で効率的な新しい発電の研究に国を挙げて(国民が肌で感じるくらい)頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
セールス外交☆
2013.05.31|shiozawa
最近、やっと政府は本腰を入れたセールス外交を行うようになりました。
そこで将来性のある、日本の製品についてご紹介。
最初はつい先日、阿倍首相が訪印した際にセールスした“隠れた名品”
■救難飛行艇US-2、輸出に向け日印首脳会談で協議 (5月28日)
27日に4日間の日程で来日したインドのマンモハン・シン(Manmohan Singh)首相と安倍晋三(Shinzo Abe)首相の首脳会談で、海上自衛隊が使用している救難飛行艇US-2のインド向け輸出に向けた議論を加速することで日印両国が合意する見通しだと、日本経済新聞(Nihon Keizai Shimbun)が27日に報じた。
輸出が実現すれば、武器輸出三原則の導入以降では日本の防衛産業が製造した完成品を他国に輸出する初めての例となり、中国の台頭をアジア地域安定への脅威と見る両国の連携強化を示すものとなる。
US-2は航続距離が4500キロ以上で、波高3メートルの荒波でも着水が可能だ。
新明和工業(ShinMaywa Industries)が開発し、約100億円で海上自衛隊に納入している。
引用:AFP BB News
そう。飛行艇です。
ジブリの紅の豚のやつです。

あまり知られていないですが、日本の飛行艇の技術は世界でトップ☆
スピードは遅いですが、超低速がとっても得意。
飛行機なのにおりたいところにピンポイントに着陸、着水できる☆
海難救助や、山火事の散水などで大活躍。
世界は広くニーズは無限に広がっていると思います。
次に紹介するのは、
哨戒機“P-1”。
■制御に光ファイバー、次期哨戒機P1を納入 川崎重工 ( 2013.3.26)
潜水艦や水上艦の動向を探知する海上自衛隊の次期哨戒機P1の納入式が26日、川崎重工業岐阜工場(岐阜県各務原市)で開かれた。
P1は現在のP3C哨戒機の後継で純国産のジェット機。
川重によると、搭載された電子機器から発生する電磁波の影響を避けるため、翼のフラップや方向舵などの制御システムに光ファイバーを通じ操縦信号を送る世界初の実用機だ。
左藤章防衛政務官は「尖閣諸島周辺での中国船の領海侵入など情勢は厳しさを増している。
P1が日本や国際社会の安全確保のため中核的な役割を果たすと確信している」と述べた。
引用:産経新聞
そう。
これはあくまで哨戒機ですから“軍用機”。
海外への輸出は今の日本の憲法ではなぜか輸出できません。
(他の国はどこも輸出できるのに日本だけはできません。)
しかし、あきらめてはいけません。
次の点がポイント☆
なお、このとき一部で国産旅客機「YSX」と共通化させると報じられたが、2001年末に防衛庁と川崎は共同で否定している。
しかし、川崎で計画中の125席クラスジェット旅客機(2007年に実現を最終決定)では、P-Xの主翼技術を利用するとしている。
また、日本航空機開発協会 (JADC) では、平成14年(2002年)度よりP-XおよびC-Xを民間旅客機(100席~150席クラス)へ転用するための開発調査を行っている。
民間機としての共用と転用の可能性があるということ。
NASAで開発された多くの技術が日常のいたるところに使われているといいます。
まさにそういった最先端技術の民間への転用は“あり”ではないでしょうか☆
そして3つ目は最新ロケット。
■JAXA、イプシロンロケット試験機の打ち上げを8月22日に設定
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は21日、イプシロンロケット試験機の打ち上げを、8月22日に試みると発表した。
打ち上げが行われる時間帯は13時30分から14時30分で、また予備日として8月23日から9月30日までが確保されている。
イプシロンはJAXAとIHIエアロスペースが開発中の新型ロケットで、かつて「はやぶさ」の打ち上げなどで活躍したM-Vロケットの後継機に当たる。
実験装置ゆえの高い打ち上げ費用を主な理由として退役したM-Vを教訓に、第1段にはH-IIAやH-IIBロケットの補助ブースターとして使われているSRB-Aを改修したものが、また第2段と第3段にはM-Vの第3段とキックモーター(第4段)を改修したものが用いられており、すでにある部品を組み合わせることで徹底した低コスト化が図られている。
また他にもH-IIAとH-IIBとの部品の共通化や、少人数で打ち上げ管制を行うなどの新機軸を取り入れており、イプシロンの打ち上げ能力はM-Vの約65%ほどだが、打ち上げ費用はM-Vの約80億円から38億円へと半額以下にまで下がっている。
また将来的には30億円以下にまで引き下げたいとしている。
もしイプシロンが計画している低コスト化を達成できれば、商業ロケットとして打ち上げビジネスを展開できる可能性もある。
しかしイプシロンの打ち上げ能力と競合するロケットは多く、価格以上の価値をどのように創出できるかが課題となろう。
引用:Sorae.jp
そう。
なんといっても打ち上げのコストが断然安い。
まだ世界で自国ロケットによる人工衛星打ち上げができるのは
たった9カ国(ロシア、ウクライナ、アメリカ、日本、中国、インド、イスラエル、イラン、北朝鮮)と
1機関(欧州宇宙機関(ESA))のみ。
新興国が急成長していますので当然、自国の人工衛星を持ち、自国の為の天気予報やGPS等々として利用したいわけです。
より安い値段で提案できる分、でっかいビジネスチャンスがあるということです。
他にも日本には世界で必要とされるものが山ほどあります。
世界中にドンドン売り込んで日本企業の景気がもっとよくなればいいですね。
ただし、”製品”ではなく“技術”の販売は禁物。
散々痛い目にあってきているわけですし、長期的に見れば自分の首を絞める失策になる可能性大。
どの国も当然強かです。
ありがとうございます。